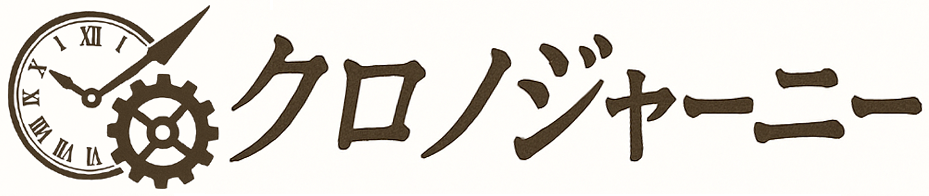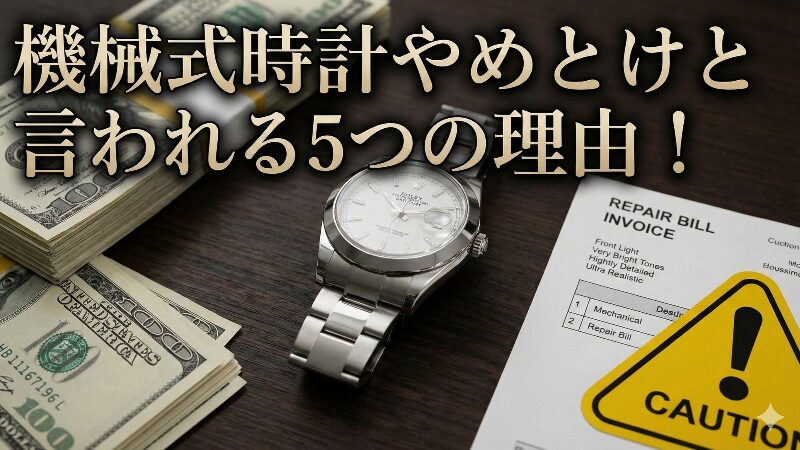機械式時計のシースルーバックから見える、規則正しく振動を繰り返す小さなホイール。そして、静寂の中で耳を澄ますと聞こえてくる、生命の鼓動にも似たリズミカルな「チクタク」という音。この小さな機械式宇宙の中心で、時計の精度そのものを司る最重要機構が「脱進機(だっしんき)」です。時計愛好家たちがムーブメントについて語る時、必ずと言っていいほど話題に上るこの精緻なメカニズムには、人類の叡智と数百年にわたる技術革新のドラマが凝縮されています。
「機械式時計はなぜ動くのか?」という根源的な問いの答えは、この脱進機の仕組みを理解することに他なりません。この記事では、時計の脱進機について、その基本的な役割から種類、そして進化の歴史を深く、そして分かりやすく紐解いていきます。現在、世界の圧倒的多数を占める標準技術「スイスレバー式脱進機」の強みと、それが内包する本質的な弱点。そして、その弱点を克服すべく開発されたオメガの「コーアクシャル脱進機の仕組み」や、そのコーアクシャル脱進機のデメリットにも公平な視点で切り込みます。さらに、日本のマニュファクチュールが世界に誇るグランドセイコーの「デュアルインパルス脱進機の評価」にも言及。「ガンギ車の役割」といった個別の部品がいかに連携し、一つの生命体のように機能しているのかを解き明かし、時計技術の奥深く、そして魅力的な世界へとご案内します。
- 脱進機の基本的な仕組みと「チクタク」音の秘密
- なぜスイスレバー式が世界の標準技術になったのか
- コーアクシャルやデュアルインパルスなど革新的な脱進機の特徴
- 機械式時計に定期的なオーバーホールが必要な技術的な理由
「脱進機は一体どのような仕組みで、どのように進化してきたのか?」その壮大な問いへの答えを、一緒に探求していきましょう。この記事を読み終える頃には、あなたの愛用する時計が、これまでとは全く違った輝きを放って見えるはずです。
なぜ正確に動く?基本的な脱進機の仕組み

機械式時計の心臓部、脱進機がどのようにしてゼンマイの力を制御し、正確な時を刻むのか。その基本構造と、「チクタク」音の秘密、そして現在の標準技術であるスイスレバー式について、より深く掘り下げて解説します。
時計の心臓部「脱進機」が持つ2つの役割
脱進機(エスケープメント)は、機械式時計のムーブメントの中で最も精巧かつ重要な機構です。その役割は、一見すると相反するような二つの極めて重要な機能に集約されます。
役割1:動力の解放を制御する「ブレーキ機能」
機械式時計の動力源は、巻き上げられた主ゼンマイがほどけようとする力です。しかし、この力は非常に強く、もし何の制御もなければ、ゼンマイは一瞬のうちに全てのエネルギーを解放してしまいます。そうなると、時計の歯車(輪列)は凄まじい勢いで空転し、針は目にも留まらぬ速さで回転した挙句、すぐに停止してしまうでしょう。これはゼンマイで走るミニカーが、壁にぶつかるまで一気に走り抜けるのと同じ状態です。
脱進機は、この強大なゼンマイの力が輪列に直接伝わる手前に立ちはだかる、精巧な「門番」あるいは「ブレーキ」として機能します。輪列の最終段にあるガンギ車を物理的にロックし、エネルギーの流れを完全に堰き止めるのです。そして、後述する調速機からの指令に応じて、その門をリズミカルに開閉し、管理された量のエネルギーだけを少しずつ輪列に流していくのです。これにより、時計の針は安定した速度で、一歩一歩進むことが可能になります。
役割2:調速機の振動を持続させる「動力供給機能」
時計の精度、すなわち「時のペース」を決定しているのは、調速機と呼ばれるユニットです。これは、規則正しく往復回転運動を行うテンプと、その動きを制御する渦巻き状のバネであるヒゲゼンマイによって構成されています。
この調速機の最大の特性は「等時性」です。これは、テンプの振れる角度(振り角)の大小にかかわらず、往復にかかる時間がほぼ一定に保たれるという物理的な性質を指します。この安定した周期こそが、時計の正確さの基準となります。
しかし、テンプも物理法則からは逃れられません。軸の摩擦や空気抵抗、ヒゲゼンマイの内部摩擦などによって、その振動エネルギーは常に失われ続けており、何もしなければ振り角は徐々に小さくなり、やがて停止してしまいます。そこで脱進機の第二の役割が重要になります。
脱進機は、堰き止めていた主ゼンマイの力の一部を、テンプが最も効率よくエネルギーを受け取れる最適なタイミングで、リズミカルに「コンッ」と押し出すように供給します。このエネルギー供給をインパルスと呼びます。失われるエネルギーをインパルスによって正確に補給し続けることで、テンプは安定した振り角を維持し、その等時性を最大限に発揮できるのです。つまり、脱進機は調速機にとっての生命維持装置、あるいはブランコを押し続ける手のような「モーター」の役割を果たしていると言えます。
このように、脱進機は「エネルギーを止める」という静的な機能と、「エネルギーを与える」という動的な機能を同時に、かつ高い次元で両立させることで、機械式時計に命を吹き込んでいるのです。
「チクタク」音の正体とは?作動音の秘密を解明

機械式時計を耳元に近づけたときに聞こえる、生命の鼓動にも似たリズミカルな「チクタク」という作動音。この音の正体こそ、脱進機が正確に機能している何よりの証拠であり、その音色やリズムには時計の健康状態に関する多くの情報が含まれています。
音を構成する3つの要素
専門的に分析すると、我々が「チクタク」と認識している音は、主に3つの異なる音響イベントの連続によって構成されています。
- ロック音:テンプの指令によりアンクルが動き、それまでガンギ車を解放していた側のツメ石とは反対側のツメ石が、回転してきたガンギ車の歯面に衝突して止める(ロックする)音
- インパルス音:ロックを解放されたガンギ車の歯が、アンクルのツメ石の斜面を滑りながら押し出す(インパルスを与える)際に発生する摩擦音
- ドロップ音:インパルスを終えたガンギ車の歯が、アンクルのツメ石から離れ、次のロックがかかるまでのごく短い時間に、わずかに空転して次の歯がツメ石の背に当たる音
これらの一連の動作が、テンプの片道(「チク」)と、その戻り(「タク」)で交互に、かつ極めて高速で繰り返されることで、我々の耳には連続した「チクタク」という一つのリズムとして認識されます。この音は、アンクルの先端にある硬質なルビー製のツメ石と、金属製のガンギ車が直接接触することで生まれる、非常にクリアで硬質な響きを持っています。
振動数と音のリズム
「チクタク」のリズム(速さ)は、その時計の振動数(ビート数)によって決まります。
- 毎秒5振動(18,000振動/時):「チク、タク、チク、タク…」と、ゆったりとしたリズム。ロービートと呼ばれ、アンティークウォッチに多く見られます
- 毎秒6振動(21,600振動/時):標準的なリズムで、多くの機械式時計で採用されています
- 毎秒8振動(28,800振動/時):「チチチチ…」と速いリズム。ハイビートと呼ばれ、高精度な現代の時計の主流です
- 毎秒10振動(36,000振動/時):「チリリリ…」と、もはや個別の音を聞き分けるのが難しいほどの高速リズム。グランドセイコーやゼニスのエル・プリメロなどが有名です
時計技術者は「タイムグラファー」という専用の計測器を使い、マイクでこの作動音を拾って分析します。音のリズムの乱れ(歩度)や、左右のバランス(ビートエラー)、テンプの振り角(アンプリチュード)などを測定し、時計の精度や健康状態を正確に診断します。まさに、「チクタク」音は、時計が自らの状態を語る言葉そのものなのです。
 MOMOMO
MOMOMOゼンマイの力を制御する3つの基本ステップ
では、具体的に脱進機はどのようなプロセスを経て、連続的なゼンマイの力を、テンプの振動に同期した断続的なリズムへと変換しているのでしょうか。その一連の動作は、CGアニメーションのコマ送りのように、3つの基本ステップに分解して理解することができます。ここでは、最も一般的なスイスレバー式脱進機を例に見ていきましょう。
ステップ1:ロック(Locking) – 静止状態
まず、時計が動作している基本的な状態は「静止」です。輪列の最後にあるガンギ車は、アンクルの片方のツメ石(入ツメ石)によって歯先をしっかりと受け止められ、回転を止められています。これにより、香箱に納められた主ゼンマイの強力なトルクは、ここで完全に堰き止められています。この状態が、次のアクションを待つ「ロック」状態です。
ステップ2:アンロック(Unlocking) – 解放の瞬間
前のサイクルでインパルスを受け、ヒゲゼンマイの復元力によって逆方向に回転してきたテンプが、その役割を開始します。テンプの軸には振り石という小さなルビーのピンが取り付けられており、これが回転してきてアンクルの先端にある二股のフォークに接触します。
振り石はフォークを「カツン」と押し、アンクル全体を軸を中心に回転させます。すると、ガンギ車をロックしていた入ツメ石が歯先から外れ、ガンギ車はついに解放されます。これが「アンロック」の瞬間です。
ステップ3:インパルス(Impulse) – 動力伝達と再ロック
アンロックによって自由になったガンギ車は、主ゼンマイの力でわずかに回転しようとします。その際、ガンギ車の歯の斜面(衝撃面)が、今まさに外れようとしている入ツメ石の斜面を滑るように強く押し出します。この「押し出す力」こそがインパルスです。
この力はアンクルを通じてフォークに伝わり、フォークはテンプの振り石を力強く押し返します。これにより、テンプは次の振動サイクルを持続させるためのエネルギーを受け取るのです。
そして、インパルスを与えると同時にアンクルはさらに回転し、その反対側の腕にあるもう一方のツメ石(出ツメ石)が、回転してきたガンギ車の次の歯の前に振り下ろされ、その動きを再び「カチッ」とロックします。これで、一連のサイクルは完了です。
テンプは与えられたインパルスによってさらに回転を続け、やがてヒゲゼンマイの力で再び逆方向に回転し始めます。そして今度は、出ツメ石側で全く同じ「ロック → アンロック → インパルス」のプロセスを繰り返します。この精密極まりない連鎖反応が、1秒間に何回も繰り返されることで、時計の針は一歩一歩、正確に時を進めていくのです。
主要部品ガンギ車・アンクル・テンプの構造
脱進機の精巧な動きは、それぞれが特徴的な形状と素材、そして明確な役割を持つ3つの主要部品の完璧な連携によって成り立っています。それぞれの部品を、より詳しく見ていきましょう。
ガンギ車(Escape Wheel)
輪列(ムーブメントの歯車群)の最後に位置し、主ゼンマイから伝達されてきたエネルギーを脱進機へと渡す最終ランナーです。素材は伝統的に真鍮が用いられることが多いですが、現代ではより硬質で加工精度の高いニッケルリン合金などが使われることもあります。最大の特徴は、のこぎりの歯や、あるいはカギ爪のような独特な形状をした歯です。この特殊な歯形は、アンクルのツメ石との間で「ロック」と「インパルス」という二つの異なる接触を、最小限のエネルギー損失で効率よく行うために、長年の研究の末に最適化された機能美の結晶です。
アンクル(Pallet Lever)
その名が示す通り、船の錨(いかり)に似た形状の部品で、ガンギ車とテンプの間を取り持つ重要な仲介役です。本体は真鍮や鋼鉄で作られ、中央の軸を中心にシーソーのように揺れ動きます。両腕の先端には、合成ルビーで作られた二つのツメ石が接着されています。ルビーが使われる理由は、ダイヤモンドに次ぐ硬度(モース硬度9)を持ち、摩擦係数が非常に低いため、金属製のガンギ車との繰り返される接触や滑りによる摩耗を最小限に抑えることができるからです。アンクルのもう一方の端は、テンプの振り石と接触するフォーク(二股の角)になっており、テンプからの動きを受け取り、テンプへと力を伝えるインターフェースの役割を担います。
テンプ(Balance Wheel)
脱進機と対になって時計の精度を司る「調速機」の心臓部です。これは、外周に重りを持つ天輪と、その軸に取り付けられた渦巻き状の極細のバネであるヒゲゼンマイから構成されます。テンプの役割は、ヒゲゼンマイの正確な復元力を利用して、物理学における「調和振動子」として、極めて規則正しい往復回転運動を行うことです。このテンプの慣性モーメント(回転のしやすさ・しにくさ)と、ヒゲゼンマイの弾性によって、時計の基本的な振動数が決定されます。軸の一部には、アンクルのフォークと接触してエネルギーの授受を行うための振り石と呼ばれるルビー製のピンが埋め込まれています。このテンプの安定した振動こそが、時計が刻む時間の「基準」となるのです。



世界標準「スイスレバー式脱進機」の強み
現代の機械式時計のムーブメントを覗き込むと、その99%以上に「スイスレバー式脱進機」という、約250年前に基本設計が確立された機構が採用されています。デジタル技術が日進月歩で進化する現代において、なぜこれほど古い設計が今なお世界の標準(デファクトスタンダード)であり続けているのでしょうか。その答えは、理論上の完璧さではなく、腕時計という過酷な環境下で使われるための、実用面における卓越したバランス感覚にあります。
この機構は、1750年代にイギリスの時計師トーマス・マッジによって発明されたレバー式脱進機が原型です。その後、19世紀にかけてスイスの時計産業で数々の改良が加えられ、大量生産に適した信頼性の高い機構として標準化されていきました。
圧倒的な強み:堅牢性と自己起動性
- 堅牢性(耐衝撃性):スイスレバー式の最大の功績は、調速脱進機の構造を非常に頑丈にしたことです。アンクルとテンプの連携は、瞬間的な接触を除いては分離しており、外部から強い衝撃が加わっても部品が外れたり、誤作動を起こしたりする可能性が極めて低い設計になっています。常に着用者の腕の動きや、時には落下といった衝撃に晒される腕時計にとって、この環境耐性の高さは、計時装置としての信頼性を担保する上で何よりも重要な要素です
- 自己起動性:時計が完全に停止した状態からでも、リューズを巻いて主ゼンマイに動力が伝わると、特別な操作やきっかけを与えることなく、自動的にテンプが振動を開始する特性を持っています。これは当たり前の機能に思えるかもしれませんが、歴史上の高精度な脱進機の中には、一度止まると時計本体を振ってテンプに初期振動を与えなければ動き出さない、繊細なものが数多く存在しました。日常的な使いやすさという観点において、この自己起動性は非常に大きなメリットなのです
もちろん、スイスレバー式は「滑り摩擦」というエネルギー効率上の弱点を本質的に抱えています。しかし、製造のしやすさ、メンテナンスに関する知識の普及、そして何よりも腕時計という携帯機器に求められる「タフさ」と「利便性」を、長年にわたって非常に高いレベルで満たし続けてきたことこそが、この方式が「偉大なる標準」として時計産業の根幹を支え続ける最大の理由なのです。
なぜオーバーホールは必要?潤滑油との深い関係


高い信頼性を誇るスイスレバー式脱進機ですが、その性能を長期にわたって維持するためには、3~5年に一度の定期的なメンテナンス、すなわち「オーバーホール(分解掃除)」が不可欠とされています。その最大の理由は、機構の動作原理が、極めて繊細な「潤滑油」の存在に大きく依存しているからです。
スイスレバー式のエネルギー伝達は、ガンギ車の歯がアンクルのツメ石の斜面を「滑りながら」押し出すことで行われます。この「滑り摩擦」は、機構の信頼性を高める一方で、エネルギーの損失と部品の摩耗という二つの大きな課題を生みます。
この課題を解決するために、時計師はツメ石の「入りの斜面」と「出の斜面」という極めて微小な面に、専用の道具を使ってピンの先端ほどの量の精密な合成油を塗布します。この油膜が、金属(ガンギ車)と宝石(ツメ石)の間の摩擦を軽減し、スムーズな動作と部品の保護を実現しているのです。
潤滑油の経年劣化という宿命
しかし、この高性能な潤滑油も時間の経過とともに劣化することは避けられません。
- 酸化と重合:空気中の酸素に触れることで油が酸化し、分子同士が結合(重合)して粘度が増していきます。サラサラだった油が、徐々にネバネバした状態になり、部品の動きに対する抵抗となります
- 乾燥・蒸発:長い年月をかけて油の成分がわずかずつ蒸発し、油膜が切れて潤滑性能が失われます
- 汚染:ムーブメント内部で発生するごく微細な金属の摩耗粉などが油に混ざり込むと、それが研磨剤のような役割を果たし、逆に部品の摩耗を促進させてしまうことがあります
潤滑油の劣化が進むと、脱進機がテンプに与えるエネルギー(インパルス)が不安定になり、テンプの振り角(アンプリチュード)が小さくなります。その結果、時計の精度は著しく悪化し、「遅れ」が目立つようになります。さらにこの状態を放置すると、部品の異常摩耗を引き起こし、最終的には時計が停止してしまいます。その場合、部品交換が必要となり、修理費用が高額になる可能性もあります。
定期的なオーバーホールは、この劣化した古い油を専門的な溶剤で完全に洗浄し、新しい油を適材適所に適量だけ注ぎ直すことで、脱進機を新品に近い最適な状態に戻すために不可欠な作業なのです。これは、機械式時計を末永く愛用するための、いわば健康診断であり、予防医療と言えるでしょう。
弱点克服への挑戦!進化した脱進機の仕組み


スイスレバー式脱進機は、腕時計の実用性を飛躍的に高めた「偉大なる標準」です。しかし、その基本設計が内包する「滑り摩擦」と「潤滑油への依存」という宿命的な弱点は、時計師たちにとって長年の課題であり続けました。20世紀後半から21世紀にかけて、素材科学と微細加工技術の劇的な進歩は、この偉大な標準を超えるための新たな挑戦を可能にしました。ここでは、オメガ、グランドセイコー、そしてゼニスといった革新者たちが、いかにしてこの難題に挑み、機械式時計の未来を切り拓いてきたのか、その闘いの軌跡を紐解きます。
オメガの革命「コーアクシャル脱進機」とは


20世紀における脱進機の進化を語る上で、ジョージ・ダニエルズ博士(1926-2011)の名を欠かすことはできません。20世紀最高の独立時計師と称された彼は、スイスレバー式脱進機が抱える「潤滑油問題」を根本的に解決することに生涯を捧げました。その探求の末、1974年に発明され、1980年に特許を取得したのが、機械式時計の歴史を塗り替えることになる「コーアクシャル脱進機」です。
「滑り」から「押し出し」へ:発想の転換
ダニエルズ博士の独創性は、スイスレバー式のエネルギー伝達における「滑り摩擦」を、よりエネルギー効率の高い「ラジアル・フリクション(接線方向の摩擦)」、すなわち部品を横から「押し出す」ような動きに置き換えた点にあります。重い家具を床で引きずって「滑らせる」よりも、台車に乗せて「転がす」方が遥かに小さな力で動かせるのと同じ原理です。この理想的なエネルギー伝達を実現するため、コーアクシャル脱進機はスイスレバー式よりも遥かに複雑な構造を持っています。
コーアクシャル脱進機の主要構成部品
- コーアクシャル・ホイール:同軸(Co-Axial)上に配置された、大きさの異なる2枚の歯車(上層のガンギ車と下層のピニオン)から成る二層構造のガンギ車
- 中間車:テンプの軸に同軸で取り付けられ、コーアクシャル・ホイールからの力を直接受け取る小さな歯車
- 特殊なアンクル:3つの異なる機能を持つツメ石が取り付けられた、独特な形状のアンクル
この複雑な機構により、エネルギー伝達の大部分が部品同士の「滑り」ではなく、ほぼ「転がり」に近い「押し出し」で行われます。その結果、摩擦抵抗が劇的に低減され、潤滑油への依存度を最小限に抑えることに成功したのです。ダニエルズ博士はこの発明をスイスの多くの大手時計ブランドに持ち込みましたが、そのあまりの革新性と製造の難しさから、長らく採用するメーカーは現れませんでした。しかし、彼の不屈の情熱と、当時スウォッチグループを率いていたニコラス・G・ハイエックの慧眼が結実し、1999年、ついにオメガが量産化に成功。キャリバー2500に搭載され、時計業界に衝撃を与えました。発明から実に四半世紀後のことでした。
これは、スイスレバー式の堅牢性や自己起動性という実用的な利点を維持しつつ、歴史上の高精度脱進機(デテント式)が持っていた高効率なエネルギー伝達の長所を併せ持たせた、まさに革命的なハイブリッド設計だったのです。
コーアクシャルのメリットとデメリットを評価
1999年の登場から20年以上が経過し、数世代にわたる改良を経て、コーアクシャル脱進機はオメガの技術的アイコンとして成熟期を迎えました。現在では、そのメリットとデメリット、そして時計業界における立ち位置も明確になっています。
メリット:長期的な信頼性と圧倒的な耐磁性能
- 長期的な精度安定性:コーアクシャル最大のメリットは、潤滑油の劣化による影響を受けにくいため、長期間にわたって安定した高い精度を維持できる点です。新品時の高い性能が、オーバーホール直前まで持続しやすいのが特徴です
- メンテナンス周期の大幅な延長:摩擦と摩耗が少ないという特性から、メーカーが推奨するオーバーホール周期は、一般的な3~5年から8~10年へと大幅に延長されています。これはユーザーにとって、維持コストと時計を預ける手間を大幅に削減できるという、非常に実用的な恩恵です
- マスタークロノメーター認定への貢献:コーアクシャル脱進機は、シリコン製ヒゲゼンマイ「Si14」と組み合わせることで、15,000ガウスという驚異的な耐磁性能を実現しました。これにより、スイス連邦計量・認定局(METAS)による厳格な認証制度「マスタークロノメーター」の基準をクリアする上で、中核的な役割を果たしています
デメリット:構造の複雑さに起因する課題
- 構造の複雑さとコスト:非常に複雑な構造を持つため、部品点数が多く、製造・組み立てに高い技術力が求められます。これは、時計本体の価格に反映される一因となります
- 調整・修理の専門性:その特殊な構造から、調整や修理にはコーアクシャル脱進機を熟知した専門技術者と専用の設備が必要です。そのため、メンテナンスは正規サービスセンターに依頼することが基本となります
- 初期モデルの技術的課題:1999年に登場した第一世代のキャリバー2500では、28,800振動/時というハイビートでの安定動作にいくつかの課題があったと指摘されることもありました。しかし、オメガはその後、振動数を25,200振動/時に最適化した改良や、完全な自社設計の新世代キャリバー8500(2007年)の開発を通じてこれらの課題を完全に克服し、技術を成熟させました
総じて、コーアクシャル脱進機は、初期コストやメンテナンスの依頼先が限定されるという点は考慮が必要ですが、それを補って余りある長期的な精度維持能力とランニングコストの低減という、実用上の絶大なメリットをユーザーに提供する、現代を代表する革新的機構と言えるでしょう。



GSの妙技「デュアルインパルス脱進機」
スイスレバー式脱進機の弱点克服という同じ目標に対し、オメガとは全く異なる独創的なアプローチで挑んだのが、日本のグランドセイコーです。2020年、同社の新世代メカニカルムーブメント「キャリバー9SA5」と共に発表された「デュアルインパルス脱進機」は、時計業界に新たな衝撃を与えました。
高効率と高信頼性の「良いとこ取り」
この機構の核心は、テンプの回転方向によって、エネルギーの伝達方式をインテリジェントに使い分ける「非対称インパルス」という、前例のない発想にあります。その目的は、歴史上最もエネルギー効率が高いとされる「デテント式脱進機」と、最も信頼性に優れる「スイスレバー式脱進機」の、それぞれの長所を一つの脱進機で両立させることでした。
- テンプが時計回りに回転する時(高効率モード):星形をした特殊なガンギ車が、アンクルを介さず、テンプに取り付けられた振り石に直接インパルスを与えます。これは、滑り摩擦がほとんど発生しない「デテント式」と同様の伝達方式であり、極めて高いエネルギー効率を誇ります
- テンプが反時計回りに回転する時(高信頼性モード):アンクルを介して間接的にインパルスを与えます。こちらは、外部からの衝撃に強く、安定した動作が保証される伝統的な「スイスレバー式」と同様の伝達方式です
この独創的なハイブリッド設計は、MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems)と呼ばれる、半導体の製造プロセスを応用した超精密加工技術によって初めて実現可能となりました。MEMSを用いることで、従来の機械加工では不可能だったミクロン単位の精度で、理想的な形状を持つガンギ車やアンクルを製造できるようになったのです。
ハイビートとロングパワーリザーブの両立
この卓越したエネルギー効率がもたらした最大の恩恵は、これまで「トレードオフの関係」にあるとされてきた二つの性能を、極めて高いレベルで両立させたことです。
- 毎秒10振動(36,000振動/時)のハイビート:振動数が高いほど、外部からの衝撃などによる時間のズレ(姿勢差)が平準化され、精度が安定します。しかし、その分エネルギー消費も激しくなります
- 80時間のロングパワーリザーブ:ゼンマイを完全に巻き上げた状態から、3日以上にわたって動き続ける持続時間。これはユーザーの利便性を大きく向上させます
デュアルインパルス脱進機は、エネルギー伝達のロスを極限まで減らすことで、ハイビートという燃費の悪いエンジンを搭載しながら、巨大なガソリンタンク(80時間のパワーリザーブ)を併せ持つことを可能にしたのです。これは、グランドセイコーが掲げる「実用性の頂点」という哲学を、技術的に具現化したものと言えるでしょう。
素材革命!シリコンが可能にした新たな進化


21世紀の脱進機の進化を語る上で、コーアクシャルやデュアルインパルスといった「機構」の革新と並行して進んだ、もう一つの巨大なトレンドが先端素材「シリコン(ケイ素)」の導入です。この素材革命は、時計の基本性能を根底から引き上げ、かつては不可能だった設計を現実のものとしました。
シリコン製部品が初めて腕時計に実用化されたのは、2001年にユリス・ナルダンが発表した「フリーク」とされています。その後、パテック フィリップ、ブレゲ、そしてスウォッチグループ(オメガやティソを傘下に持つ)が共同で研究開発を進め、急速にその応用範囲を広げていきました。
シリコンが持つ時計部品としての卓越した特性
なぜシリコンがこれほどまでに時計製造の世界を変えたのか。それは、従来の金属素材(主に鋼鉄や真鍮の合金)が持っていた数々の弱点を克服する、卓越した物理特性に理由があります。
- 完全な非磁性:スマートフォン、PC、バッグのマグネットなど、現代生活に溢れる磁気は、金属製のヒゲゼンマイを磁化させ(磁気帯び)、精度を著しく悪化させる最大の原因の一つです。シリコンは磁性の影響を全く受けないため、この問題を根本的に解決します
- 軽量かつ高硬度:鋼鉄の約3分の1の軽さでありながら、高い硬度を誇ります。これにより、部品の慣性を小さくでき、エネルギー効率の向上や耐衝撃性の改善に繋がります
- 潤滑油が不要:表面が極めて滑らかで摩擦係数が低いため、部品同士が接触する箇所でも潤滑油を必要としない場合があります。これは、オーバーホールの負担を軽減し、長期的な性能維持に貢献します
- 優れた弾性と耐疲労性:金属バネのような塑性変形(へたり)が起こりにくく、長期間にわたって安定した弾性を維持します。特にヒゲゼンマイの素材として理想的です
- 高い温度安定性:温度変化による寸法変化(熱膨張)が鋼鉄の約5分の1と非常に小さく、温度変化による精度の誤差を大幅に低減します
- 超精密加工が可能:前述のMEMS技術を用いることで、ミクロン単位の精度で、極めて複雑で理想的な形状の部品を設計通りに製造できます
このシリコン素材の登場は、まず時計の精度を司るヒゲゼンマイに革命をもたらしました。現在では、オメガの「Si14」や、パテック フィリップの「Spiromax®」など、多くのトップブランドがシリコン製ヒゲゼンマイを中核技術として採用しています。さらに、その応用はアンクルやガンギ車にも広がり、デュアルインパルス脱進機のような革新的な機構の実現を技術的に下支えしています。素材そのものから時計のあり方を見直すというアプローチは、脱進機の進化に新たな地平を切り拓いたのです。



未来の形?ゼニスの革新的オシレーター
これまでの脱進機の進化が、既存の部品の構造や素材を改良する「改善」の歴史であったとすれば、2017年にゼニスが発表した「ゼニス オシレーター」は、その概念を根底から覆す「発明」と言えるでしょう。
30点の部品を、わずか1点に統合
この機構の最大の特徴であり、衝撃的な点は、従来であれば約30個の個別の部品で構成されていたテンプ、ヒゲゼンマイ、アンクルといった調速・脱進機構全体を、厚さわずか0.5mmの単結晶シリコン製ウエハー一枚に集約してしまったことです。
これは「コンプライアント・メカニズム(弾性機構)」と呼ばれる、航空宇宙産業などで用いられる最先端の原理を応用したものです。蝶番(ヒンジ)やバネのような機能を、別々の部品を組み合わせるのではなく、一体成型された構造体そのものの「たわみ」や「しなり」によって実現する技術です。このゼニス オシレーターでは、一枚のシリコン部品が、素材自体の弾性を利用して極めて高速に振動し、その一部がガンギ車と直接噛み合うことで、時を刻むのです。
この革命的な構造は、機械式時計が300年以上にわたって格闘してきた根本的な問題群を、いわば「ルールを変える」ことによって一挙に解決しました。
- 接触・摩擦・摩耗・潤滑からの解放:部品点数が1つであるため、従来の機構が抱えていた軸の摩擦、部品同士の衝突、そして潤滑といった問題が原理的に存在しません
- 驚異的な高振動と高精度:その振動数は毎時129,600振動(36Hz)と、一般的な機械式時計(28,800振動/時)の4倍以上という超高振動数を実現。これにより、日差±1秒以内という、クォーツ時計に匹敵する驚異的な精度を機械式で達成しました
ゼニス オシレーターは、3世紀以上にわたる時計製造の歴史、すなわち「いかに調速機を動力源の干渉から解放するか」というテーマに対し、部品を無くし「完璧に制御された干渉」を作り出すという、全く新しい回答を示したのです。もちろん、長期的な素材疲労や衝撃に対する耐久性、そしてメンテナンス(基本的にはモジュールごとの交換になると予想される)など、実用化に向けてはまだ未知数な部分もありますが、これが未来の機械式時計の一つの姿を予感させる、まさに革命的な発明であることは間違いありません。
総括:進化の歴史で辿る脱進機の仕組み
この記事では、機械式時計の心臓部である脱進機の仕組みと、その進化の歴史を辿ってきました。最後に、今回の内容のポイントをまとめて振り返ってみましょう。



- 脱進機はゼンマイの力を制御する「ブレーキ」とテンプを動かし続ける「モーター」の二役を担う
- 時計の「チクタク」音はアンクルのツメ石がガンギ車を叩く音であり、時計の生命の鼓動そのもの
- ロック・アンロック・インパルスという3ステップの精密な連鎖反応で正確な時を刻んでいる
- スイスレバー式脱進機は衝撃に強く使いやすいため、現代の機械式時計における世界の標準技術となった
- スイスレバー式は滑り摩擦を利用するため潤滑油が必須で、その劣化がオーバーホールの主な理由である
- オメガのコーアクシャル脱進機は摩擦を劇的に減らし、オーバーホール周期を8~10年へと大幅に延長した
- コーアクシャルは構造が複雑でコストが高いが、長期的な信頼性という大きなメリットを提供する
- グランドセイコーのデュアルインパルス脱進機は、高効率な直接衝撃と高信頼性な間接衝撃を使い分ける
- このハイブリッド方式により、ハイビートとロングパワーリザーブという相反する性能の両立を実現した
- シリコン素材の導入は、非磁性・軽量・無潤滑といった利点をもたらし、脱進機の性能を飛躍させた
- ゼニスのオシレーターは、多数の部品を単一のシリコン部品に統合し、摩擦や摩耗の問題を原理的に解決した
- 脱進機の進化の歴史は、いかに調速機(テンプ)の自由な振動を妨げないかという闘いの歴史であった
- 現代の革新は、過去の偉大な設計思想を、最新の素材と加工技術によって再解釈・統合する試みである
- 脱進機の仕組みを理解することで、機械式時計の技術的な価値や奥深さをより一層感じることができる
- 自分の時計に搭載されている脱進機を知ることは、その時計の個性や哲学を知ることに繋がる
今回は、機械式時計の心臓部である脱進機の仕組みと、その進化の歴史について詳しく解説しました。
日頃耳にする「チクタク」という音の秘密から、スイスレバー式がなぜ世界の標準であり続けるのか、そして現代の革新的な脱進機が何を目指しているのか、その奥深い世界をご理解いただけたのではないでしょうか。
脱進機の仕組みを知り、定期的なオーバーホールの重要性を再認識された方も多いかと思います。具体的な料金の相場や、信頼できるお店の選び方については、こちらの記事が参考になるでしょう。
また、シリコン素材の登場で注目される時計の耐磁性能について、より深く知りたい方にはこちらの記事もおすすめです。